公園や児童館に行くたびに、口酸っぱく伝えている「順番」。
何度言ってもお友達のオモチャを奪ったり、堂々と割り込みをしたりして、ママやパパは戸惑い、不安や申し訳なさを抱えているのではないでしょうか。
しかし、同じ悩みを持つ親は多く、これは決して育て方の問題ではありません。
この記事では、2歳の子どもが順番を守れない理由を脳の発達からわかりやすく解説し、今すぐ使える関わり方や対策を具体的に紹介します。
「なぜ?」「どうしたら?」がスッキリ理解でき、今日からの接し方がぐっと楽になるはずです。
順番を守れないのは躾(しつけ)の問題でも性格の問題でもありません。「脳」に大きな原因が隠されています!
なぜ?2歳児が順番を守れない脳の仕組み
2歳の子どもが順番を守れない最大の理由は、我慢や切り替えを担当する前頭前野がまだ未発達で、感情より先に理性が働かないためです。
さらに、目の前の刺激に強く反応しやすく、記憶を一時的に保持する力(ワーキングメモリ)が弱いため、「順番を待つ」という複数の情報を同時に処理できません。
その結果、今すぐやりたい気持ちが一気にあふれ、順番を奪ったり、押したりする行動につながります。
また、状況をうまく理解できないことから不安や混乱が起こり、パニックや癇癪が起きやすくなるのも、この時期には自然なことです。
つまり順番を守れないのは“できないのではなく、まだ脳が追いついていないだけ”で、成長とともに確実に改善していきます。
順番理解の発達段階|3歳、4歳、5歳でどう変わる?
当然ですが、年齢と同時に脳も成長していきます。今は無理でも、来年には、再来年には…とできることが増えていきますので、順番に対する不安も薄れていくかと思います。
・3歳~4歳
順番という“ルールそのもの”の理解が少しずつ芽生えますが、感情が先に動きやすく、状況によって守れたり守れなかったりと不安定さが残ります。
・4~5歳
4歳になると前頭前野の働きが強まり、我慢や見通しを持つ力が育つため、順番を待つ場面でも落ち着きやすくなり、トラブルが大幅に減っていきます。
・5歳~
そして5歳を過ぎる頃には、感情のコントロールや相手の気持ちを考える力が伸び、社会的なルールをより安定して守れるようになります。
このように順番理解は年齢とともに段階的に育つもので、繰り返しの経験と周囲のサポートが重なることで、確実に身についていきます。
今すぐできる!2歳児が順番を理解しやすくなる関わり方
2歳の子どもに順番を理解してもらうには、まず「少しだけ待てた」という成功体験を小さく積み重ねることがとても効果的です。
ポイントは、①事前にルールを説明する ②短く端的に声掛けをする ③少しでも待てたら褒める
①事前にルールを説明する
できれば家や公園に到着する前に(遊びたいものを目にして、こどもの脳が「やりたい!」に縛り付けられない時に)、順番についてお話してみましょう。「前にお友達が並んでいたら、後ろに並ぼうね」と定期的にルールについてお話してみましょう。
②短く端的に声掛けをする
「次は〇〇くんの番ね」と短く区切った声かけが、幼い脳には伝わりやすく負担も少なくなります。もし説明しても動けない時は、一度気持ちを受け止めてから行動を調整すると、子どもは落ち着きを取り戻しやすくなります。「そうだね、もう一回やりたくなったんだよね。」など、スキンシップを図りながらお話してあげるとより効果的です。
③少しでも待てたら褒める
例え連日割り込んでしまっても、昨日と比べて長く待てた場合は、立派な成長。欲望に忠実で扁桃体(ストレスを感知する場所)が敏感なイヤイヤ期に、「やりたい!」を抑えることは、かなり難易度が高いです。昨日と比較して我慢できた点があれば、「その行動が正解だよ」と褒めて教えてあげましょう。
もしも順番待ちのトラブルを減らすには、混雑しにくい遊び場を選ぶなどの環境の工夫も大きな助けになります。また、絵本や動画などで「順番」について学ぶこともオススメです。頻繁に教えると、順番を守るとはどういうことか、割り込むとはどういうことか客観的にわかるようになっていきますよ。
順番を「守らせる」より「一緒に覚えていく」という姿勢で関わることで、子どもは安心し、順番のルールを少しずつ身につけていきます。
例:)公園・児童館でのトラブルを防ぐ方法
公園や児童館では、滑り台・順番待ちの車・キッチンセットなど、1つの遊具に複数の子が集まる状況が多く、2歳児にはとても刺激の強い環境です。
例えば滑り台では、「早く滑りたい!」という気持ちが高まり、前の子を追い越して階段を登ったり、背中を押してしまうことがよくあります。
こうしたトラブルを防ぐには、まず親が少し早めに状況を察知することがポイントです。
滑り台が混んでいると感じたら、あえて行列が短いときに誘導したり、「3回滑ったらブランコに行こうか」と次の行き先を決めておくと、焦りや刺激が減りやすくなります。
また、順番が絡む場面では、事前に短い予告を入れることが特に効果的です。
「次は〇〇ちゃんね」「あと1回で帰るよ」「このお皿使ったら交代しようね」など、具体的な回数や物を使った伝え方は、2歳児の脳でも処理しやすい情報です。
もし順番を抜かしてしまったり、おもちゃを奪ってしまった場合でも、いきなり叱ると子どもはパニックになり状況が悪化しやすいもの。
その場では、
- 「やりたかったんだね」(気持ちの受け止め)
- 「じゃあお友だちが終わったら貸してもらおうね」(次の行動を提案)
という2ステップで関わると、落ち着きを取り戻しやすくなります。
もしもそれでも癇癪が静まらない場合は、ほぼ2人きりになれる静かな場所に移動し、好きなだけ大声で泣かせてあげてください。大声で泣くというのは、脳の癇癪を落ち着かせるためにやってるんです。
「そうだね、やりたかったね」と声を掛けながら安全を見守ってあげててください。次第に子どもも冷静になってきて、気持ちを切り替えられるようになります。
また、保育園の先生がよく使う方法として、親が仲介に入ることも有効です。
例えば、キッチンセットで2歳児同士が「使いたい!」とぶつかりそうなとき、
「じゃあ、〇〇ちゃんは“赤いフライパン”、△△くんは“青いお皿”ね。次に交換しよう」
というように、役割と順番を大人が代わりに言語化してあげると、争いが一気に減ります。
さらに、トラブル予防のためには、場所の選び方も非常に重要です。
夕方の公園は混みやすいので、午前中の人が少ない時間帯を狙う、児童館なら混雑のピークを避けるなど、環境選びだけで順番争いは驚くほど減ります。
このように、公園や児童館でのトラブルは、
- 早めの観察
- 事前のひと声
- 親が小さく環境調整
- アナウンス役として順番を“見える化”
の4つで大幅に防ぐことができます。
どれも今日からすぐに試せる方法ばかりなので、親子で安心して楽しく遊ぶために、ぜひ取り入れてみてください。
まとめ:どうしたら子どもは順番を守れるようになる?
2歳が順番を守れない理由は、性格ではなく脳の発達段階にあり、前頭前野が未成熟なため我慢や見通しを持つ力が追いつかないことが大きな要因です。
この時期の子どもは刺激に反応しやすく、「今すぐやりたい」という衝動が最優先されるため、順番を抜かしたり、おもちゃを奪ったりする行動が自然と起こりやすくなります。
しかし順番理解は年齢とともに確実に育つ力であり、親の関わり方を少し工夫することで子どもの成長がスムーズに進んでいきます。
▼子どもが順番を守れるようになるためのポイント
順番を守る力は「しつけ」で一気に身につくものではなく、脳の発達と経験の積み重ねでゆっくり育つ能力です。そのため、守れない瞬間だけを見るのではなく、長い目で子どもの成長を捉える視点がとても大切になります。親が叱ることに力を入れるより、環境を整え、分かりやすく言語化し、成功体験をサポートするほうが、子どもは安心して順番を理解できるようになります。
今日できなかったことが、来月できることもありますし、5歳を過ぎれば驚くほど落ち着いて順番を待てるようになる子が多いのも事実です。「今はまだ脳が追いついていないだけ」という視点を持つことが、親の心を軽くし、子どもの成長を見守る大きな力になります。
順番を守る力は、少しずつ、確実に育っていく。
それを信じて関わることが、子どもにとって何よりのサポートになるのです。
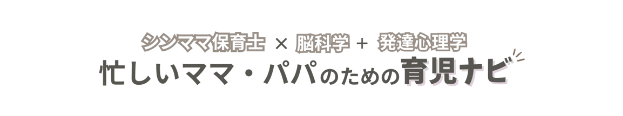


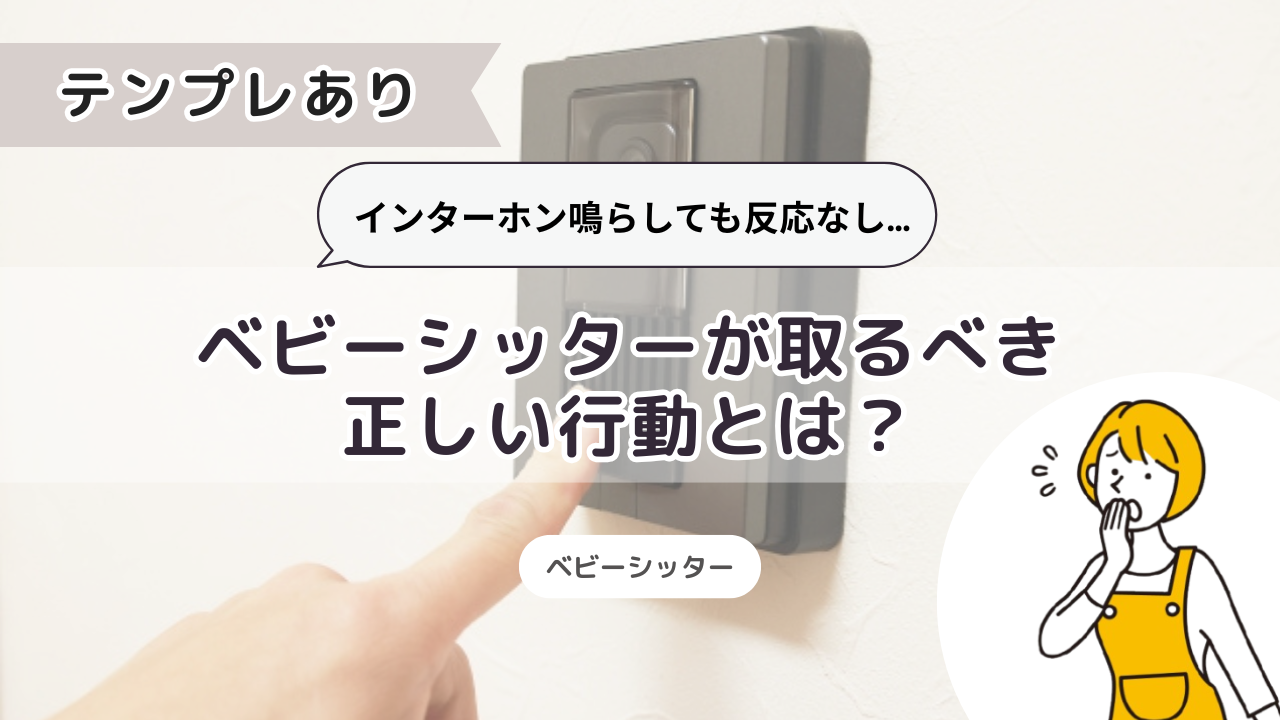
コメント