赤ちゃんがパパを見て泣いてしまう…そんな「パパ見知り」に悩んでいませんか?
「嫌われたのかな」と不安になるパパや、対応に困るママも多いはずです。
本記事では、発達心理学や脳科学の視点から「パパ見知り」の本質に迫ります。!具体的な接し方や実践例も併せてご紹介。
読めば、「泣かれても大丈夫」と思えるようになるヒントが見つかりますよ。
そもそもの疑問!どうしてパパ見知りするの?
赤ちゃんがパパを見て泣く「パパ見知り」は、単純に人見知りの一種です。
どうして赤ちゃんはパパやママ以外の人を見ると泣いてしまうのでしょうか。ヒントは「動物としての本能」にありました。
動物は基本相手を威嚇する時に目を合わせます。例えば我々人間に近い猿もそうですよね。野生の猿とは目を合わせるな、というのは有名です。
動物は目が合うと反射的に恐怖を感じ、警戒心が高まるのです。
実は人間も同じで、人と目が合うと扁桃体という脳の一部が働きます。
赤ちゃんは前頭前野が未発達のため、感情をコントロールすることができず、目が合うと反射的に恐怖を感じて泣いてしまうのです!
そのため、たとえ毎日顔を合わせているパパでも、突然泣いてしまうことがあるのです。
これは決して「嫌い」だからではなく、むしろ関心を持ち始めた成長のサインです。
\ひとくちメモ/
赤ちゃんに、ママと見知らぬ人が写った画面を見せ、どちらの方が長い時間見るか実験しました。
すると人見知り前の赤ちゃんはジーっとママの顔ばかり見ましたが、人見知り中の赤ちゃんは頻繁に知らない女性の顔を見ました。顔の中でも特に「目」を見ていることがわかりました。これにより、ママ以外の人には興味があるため目を見つめますが、実際目が合うと少しずつ恐怖に感じてしまうのです。(同志社大学の赤ちゃん学研究センター)
「嫌われてる」わけじゃない!安心できる存在になるには
赤ちゃんに泣かれると「嫌われてるのかな」と感じてしまいますよね。
でも、赤ちゃんが泣くのは、見慣れない表情や声に警戒するのは、本能として自然な反応ですし、相手に関心を持っている証拠でもあります。
そこで大切なのは、「この人は安心できる存在だ」と赤ちゃんに感じてもらうこと。
ママと笑顔で話している姿を見せるだけでも、信頼感はぐんと高まります。
また、無理に抱っこせず、少し距離をとって優しく声をかけてみましょう。
赤ちゃんは時間をかけて安心できる相手を見極めている途中なのです。
実践編:パパとママができる具体的な対策
パパ向けの対策
泣かれるのが怖くて距離をとってしまう…そんな気持ち、よくわかります。でも大切なのは、赤ちゃんのペースに合わせて「近づくこと」なんです。
具体例
・ママと一緒に笑顔で話す時間を作る
赤ちゃんは「ママが安心して接している人=安全な人」と感じやすいです。無理に抱っこせず、ママと楽しそうに会話する姿を見せましょう。
・毎日決まった時間に「おはよう」「いってきます」など声をかける
短くても毎日決まったタイミングで声をかけることで、赤ちゃんに「この人はいつもいる安心な存在」と認識してもらえます。
・赤ちゃんのそばで絵本を読み聞かせる
抱っこしなくても、少し離れた場所から声で安心感を伝えられます。優しいトーンで語りかけることで親しみを感じてもらえます。
・オムツ替えや沐浴など育児に積極的に参加する
最初は泣かれるかもしれませんが、繰り返し関わることで「世話をしてくれる=信頼できる人」と思ってもらえます。
・赤ちゃんと目線を合わせてにっこり笑う
いきなりジッと見つめるのではなく、ふと目が合った時に優しくほほえむことで、「怖くない存在」と感じさせることができます。
ママ向けの対策
パパ見知りが始まると、どうしてもママへの負担が大きくなりますよね。
でも実は、ママこそがパパと赤ちゃんをつなぐ「安心の架け橋」になれる存在です。
例えば、パパが赤ちゃんに声をかけた時は、そばでにこやかに見守るだけでも効果的です。「パパは安心できる人なんだよ」と笑顔で語りかけるのも信頼形成に役立ちます。
また、パパが関わってくれたときは、できるだけ肯定的に声をかけてみましょう。
ママのちょっとした言葉が、パパの自信を大きく育ててくれます。
赤ちゃんとパパの関係は、ママの温かなサポートでぐっと近づきますよ。
また、少しずつ慣れてきたら、ママが完全に姿を隠すというのも効果的です。子どもの中でママが1番だとしても、ママが不在でパパしかいない状況になったら、パパが1番になります。同じ部屋にいるのはもちろん、ちょっとした気配でもママを感じると泣き求めてしまうので、家をしばらく出るのも一手です。
パパ見知りについてのQ&A
Q.生まれてからすぐに父親が積極的に育児していればパパ見知りは減る?
➡パパ見知りの可能性は「低くなる」傾向があります。
ただし、完全に防げるとは限りません。
赤ちゃんは、生まれた直後から「安心できる人」「よく接してくれる人」を認識し始めます。
抱っこや声かけ、授乳の補助、おむつ替えなどで関わる時間が多い人に対して、「安全基地」としての信頼感を形成していきます。
パパが新生児期からスキンシップを取り、日常的に関わることで、赤ちゃんにとって「いつもいる、安心できる存在」と認識されやすくなります。
が!それでもパパ見知りが起きる可能性はあります。
ただし、赤ちゃんの脳の発達段階によっては、誰に対しても人見知りが出る時期があります(多くは生後6〜9ヶ月ごろ)。
たとえ毎日一緒にいても、ふとしたタイミングで「なんかいつもと違う!」と感じ、泣いてしまうこともあります。
これは「嫌い」や「拒否」ではなく、成長過程の自然な反応。一時的なものですので、パパは落ち込まず、関わりを続けてあげてくださいね。
Q.なんでママ見知りはしないの?
➡ママは本能的・身体的・感覚的に「安心の象徴」としてインプットされやすいから
■ママと赤ちゃんはホルモンでつながっている
出産後、ママの体では「オキシトシン(愛着ホルモン)」が多く分泌されます。これは母乳分泌を促すだけでなく、赤ちゃんへの愛着を強める働きがあります。
一方、赤ちゃん側も、授乳や肌のふれあいを通じてオキシトシンが分泌され、ママ=安心できる人として強く認識されます。
このホルモンの相互作用は、ママと赤ちゃんの信頼関係をより早く・強く形成するのです。
■赤ちゃんはニオイや声でママを識別している
赤ちゃんは生まれてすぐ、ママの体のにおいや声の周波数を識別できると言われています。
特に母乳のにおいは赤ちゃんにとって強い安心材料であり、ママの存在を本能的に覚えています。
これは胎内にいたときの記憶や感覚がベースになっているとされます。
■3. 脳の仕組み上、赤ちゃんは「より多く接した人」に安心する
赤ちゃんの脳では、扁桃体(恐怖や警戒心をつかさどる部分)が発達途中のため、「よく見る・聞く・触れる」人を安全な人と記憶していきます。
ママは出産直後から授乳や寝かしつけなどで赤ちゃんと長時間密接に関わります。
この圧倒的な接触時間の差が、ママ見知りが起こりにくい理由でもあります。
Q.絶対ママじゃなきゃダメなの?
➡子どもは状況に応じて順位付けを柔軟に変えることができます。
子どもの中でママが1番だとしても、ママが不在でパパしかいない状況になったら、パパが1番になるんです。そうやって子どもは、その場で最も頼りになる存在に愛着を示します。
もしも子どもの視界にママの姿が映っていた場合、またはママの気配を近くに感じたなら、子どもはママを追い求める可能性が高いので、安心してお任せしてみてもいいかもしれません。
まとめ
赤ちゃんに泣かれると、「嫌われたのかな…」と不安になるパパも多いですよね。
でも、パパ見知りは赤ちゃんの発達において自然で健全なステップですから!
赤ちゃんは、知らない存在に対して本能的に警戒心を抱きます。
特に「目が合う」ことに恐怖を感じるのは、動物としての自然な反応です。前頭前野が未発達な赤ちゃんは、それを理性で制御することができません。それでも赤ちゃんはパパに「関心がある」からこそ、泣くこともあるのです。
パパ見知りを乗り越えるには、焦らず、日々の関わりを大切にすることが何より大切です。
ママの存在もまた、安心感を広げる大きな力となります。
本記事の重要ポイントまとめ
・赤ちゃんが見知らぬ人に泣くのは生存本能による自然な反応
・「目が合う=威嚇」と感じ、脳の扁桃体が恐怖を引き起こす
・母親はにおいや声、ホルモン(オキシトシン)で特別な存在に認識されている
・パパは「関心があるからこそ泣かれる」こともあると理解しよう
・パパが安心できる存在になるには、無理せず、少しずつ関わることが大事
・絵本の読み聞かせや声かけなど、スキンシップの機会を毎日積み重ねよう
・ママは笑顔でパパと赤ちゃんをつなぐ「安心の架け橋」になることができる
・見知りは「信頼の一歩手前」。だからこそ、成長のサインとして温かく受け止めよう
「生まれた時から一緒にいるじゃん!」と、人見知りをされたパパにとってはつらい時期かもしれません。
でも、それは赤ちゃんが心を開こうとしている証でもあるのです!
「信頼関係を築く前の大切な段階」なんです!
ママとパパが一緒に寄り添い、赤ちゃんのペースに合わせて関わることで、親子の絆は少しずつ、でも確実に深まっていきます。
泣かれても大丈夫。笑顔でそっと、手を差し伸べてあげましょう。
家族の時間は、こうして育まれていくのです。
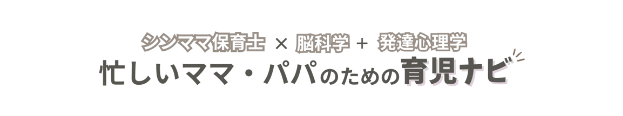
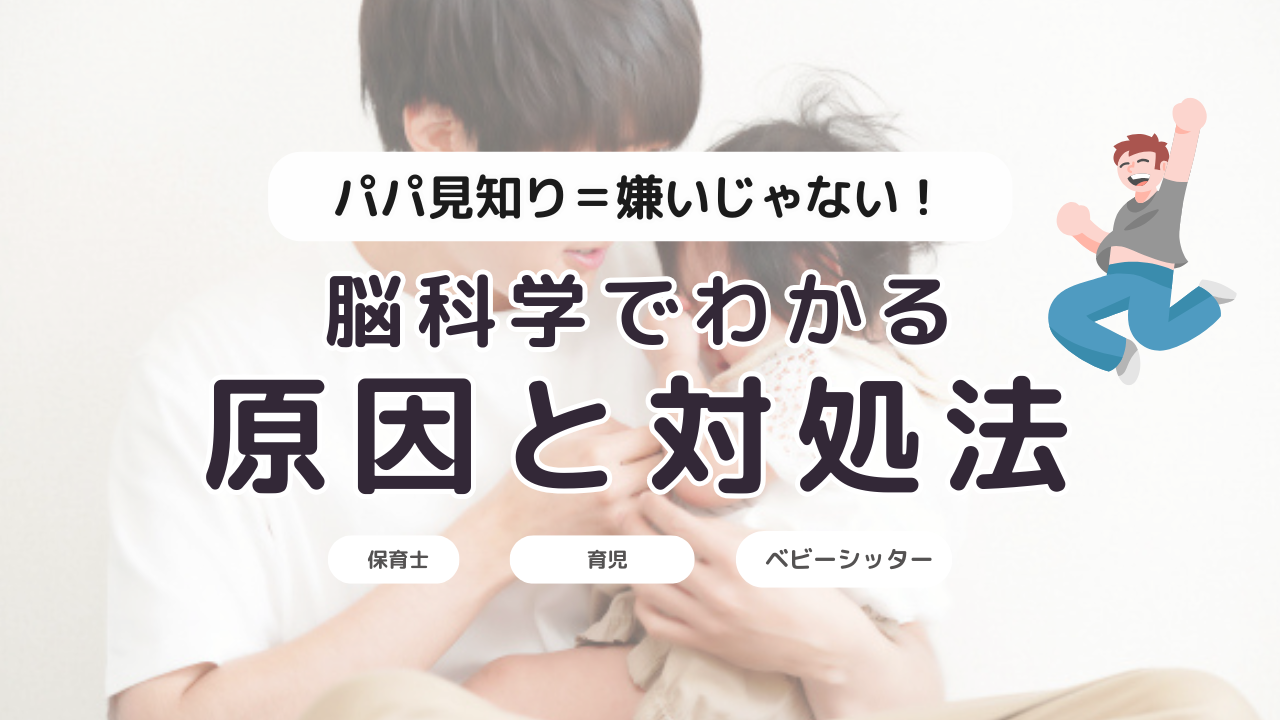

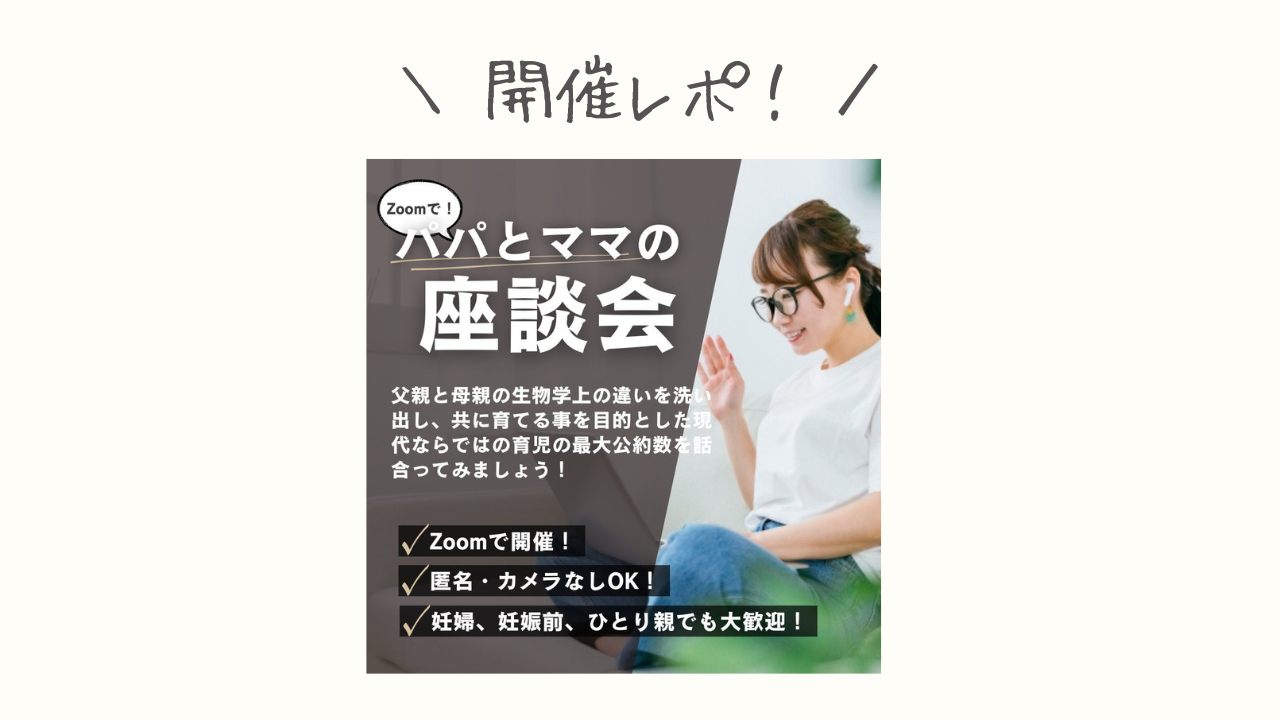
コメント