夜寝ている時。例え深夜でも子どもが咳をしていれば、気になって起きてしまう。
大丈夫かな?咳込みすぎて眠りが浅くなってないかな!?明日病院!?
なんて心配事が一度に流れ込んでくるけど、
…あれ?パパはそんなこと気にせず、いつも通り寝ている。(モヤッ
なんていうことありますよね。
どうしてママは気が付くのに、パパは気が付かないんでしょう。
子どもを想う気持ちや責任感の違いじゃないの?
いえいえ、実は脳科学や生物学的に、こんなメカニズムがあるんです。
ママが気づく理由は、脳が出産を通して進化したから!
一番はこれです。出産や育児を経験すると、ママの脳は子どもの声や小さな物音に敏感に反応するようになったから。特に扁桃体と呼ばれる感情や危険察知を司る部分が活性化し、赤ちゃんの泣き声や夜中の咳を即座にキャッチする仕組みが働くのです。また、ママはホルモンの影響で深い眠りに入りにくく、眠っていても浅い睡眠の状態が続きやすいとされています。そのため、子どものわずかな咳や寝返りにも反応して目が覚めてしまうのです。要は出産を通して、「育児脳」に進化したんですよね。子どもを守るために備わった自然な適応です。決してママが神経質だからでも、パパが無関心だからでもなく、脳科学的に説明できる現象なのです。
\ひとくちメモ!/
咳の大きさは70~90dB程度と言われています。 これは目覚まし時計や電話のベル、玄関チャイムと同じくらいの音量です。
え、そのくらいの音量なら気が付けよ、って思うかもしれません。
が。
男性は、以下の理由があるんです。
パパが気づかないのは「責任感の問題」ではない
夜中に子どもの咳に気づかないパパを見ると「無関心なのでは」と思ってしまうかもしれません。最早イラつきを覚えることだってありますよね。ですが、実際には責任感の有無ではなく、脳と体の仕組みの違いが大きく関わっています。
男性は深い眠りに入りやすい性質があり、環境の変化や小さな物音に対して反応が鈍くなる傾向があります。これは進化の過程で、昼間に外で働き、外敵から家族を守る役割を担ってきた名残とも考えられています。
つまり、パパが起きないのは怠けているのではなく、体が備えた自然な仕組みによるものなのです。
こうした違いを知るだけで「責める気持ち」が和らぎ、夫婦で支え合う視点が持てるようになります。パパはママと違って子どもが生まれたとて大きな体の変化はありませんからね。デフォルトでこれです。学習すれば変わる。そういうものなんです。
生物学的に見る『ママとパパの役割分担』
人類の長い進化の歴史を振り返ってみれば、ママとパパには本能的に異なる役割があるよな、とお察しいただけるかと思います。
ママは子どもを産み、育てる存在として、赤ちゃんの泣き声や体調の変化に敏感に反応できる脳と体の仕組みを持っています。一方でパパは、日中に狩りや外敵からの防衛を担うため、体力を温存するよう深い眠りに入りやすい傾向があります。つまり、ママは「命を守るセンサー」、パパは「外で戦う力」を備える形で、それぞれ子どもを守るための分担が成立してきたのです。
現代の生活では外敵はいませんが、ある意味、「子どもの睡眠を妨げる咳」というのは外敵ですよね。そういう意味では根元にある本能的なものがママは働いてしまうのかもしれません。
この本能的な違いは脳や睡眠パターンに残っています。役割の差は「どちらが正しいか」ではなく「補い合う仕組み」と捉えることが、子育てを楽にする第一歩なのです。
イライラを減らすためにできる工夫
夜中に何度も起きて子どもの咳に対応していると、ママはどうしても睡眠不足になり、パパがぐっすり眠っている姿にイライラが募ってしまいます。けれども「パパが起きないのは脳と体の仕組み」と理解するだけで、責める気持ちはかなり和らぎます。
しかしあまりにも子どもの咳が続いてしまうとママ自身も十分な睡眠がとれず、負担が大きすぎますよね。そんな時は、あらかじめ交代制を取り入れたり、パパが朝の支度や日中の家事を分担するなど、夜に偏る負担を調整する工夫が効果的です。また、寝室の加湿や子どもの寝姿勢を整えることで咳を減らし、起きる回数自体を少なくできることもあります。イライラの背景には「自分だけ頑張っている」という感覚があるため、夫婦で小さな役割分担を共有することが、気持ちを楽にする大きな一歩になるのです。
▼子どもの咳にイライラしてしまった時はこちら!
まとめ
子どもが夜中に咳をするたび、ママだけが目を覚まし、隣で眠るパパはぐっすり眠ったまま――この状況、不満を覚えたりイライラしてしまうことありますよね。
しかし、実はこれは「パパの責任感の有無」ではなく、脳や体の仕組みによって生じている自然な現象なのです。
ママは出産や育児を経験すると、赤ちゃんの泣き声や体調の変化に敏感に反応するように脳が変化します。扁桃体や聴覚野が活性化し、浅い睡眠になりやすいホルモン環境の影響もあり、夜中のわずかな咳や寝返りにもすぐ反応できる状態になります。これは「育児脳」とも呼ばれる適応で、子どもの命を守るための自然なセンサーなのです。
一方でパパは、脳と睡眠の仕組みによって深い眠りに入りやすい傾向があり、環境の小さな変化には気づきにくくなります。これは決して無関心ではなく、生物学的には外敵から家族を守るため、体力を温存する役割を担ってきた名残と考えられています。
こうした違いを理解することで、「なぜ自分だけ起きてしまうのか」というモヤモヤが解消され、パパを責める気持ちも和らぎます。むしろ、夫婦それぞれの仕組みを知ることで、補い合う子育てが可能になるのです。
\今回の記事で重要なポイント!/
- ママはホルモンや脳の働きにより、子どもの咳に敏感になりやすい
- パパは深い眠りに入りやすく、無関心ではなく仕組みの違いで起きにくい
- 生物学的に「ママはセンサー」「パパは体力保持」と役割が分かれてきた
- 役割の違いを理解するだけで、イライラが減り、夫婦の協力体制が築ける
- 交代制や日中の分担、環境改善でママの負担を軽減する工夫が有効
つまり、「パパが起きない=責任感がない」ではなく、「ママが敏感=本能的な適応」なのです。
子どもの咳に気づくのは、ママだからこそ持つ特別な力。役割の違いを前向きにとらえ、夫婦で協力して子どもの夜を守っていきましょう。
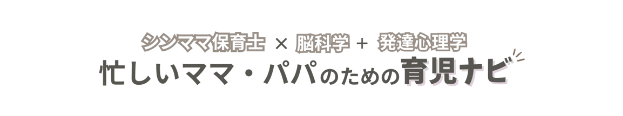
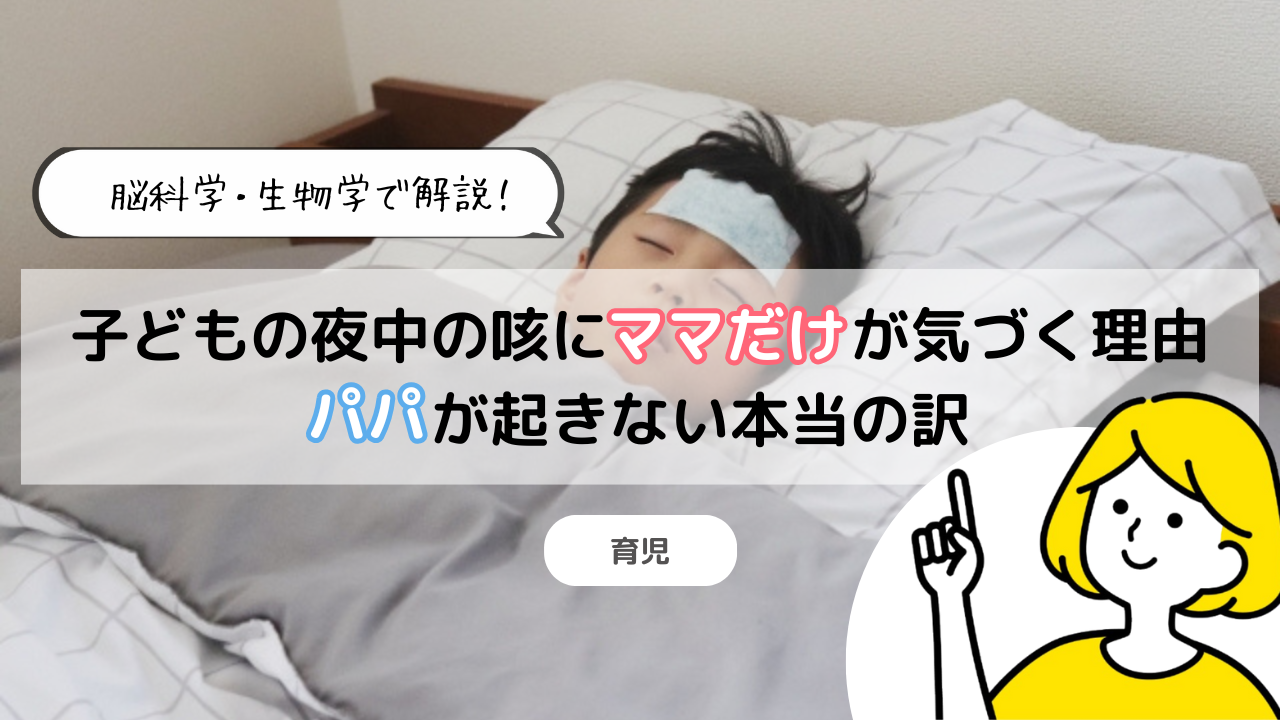

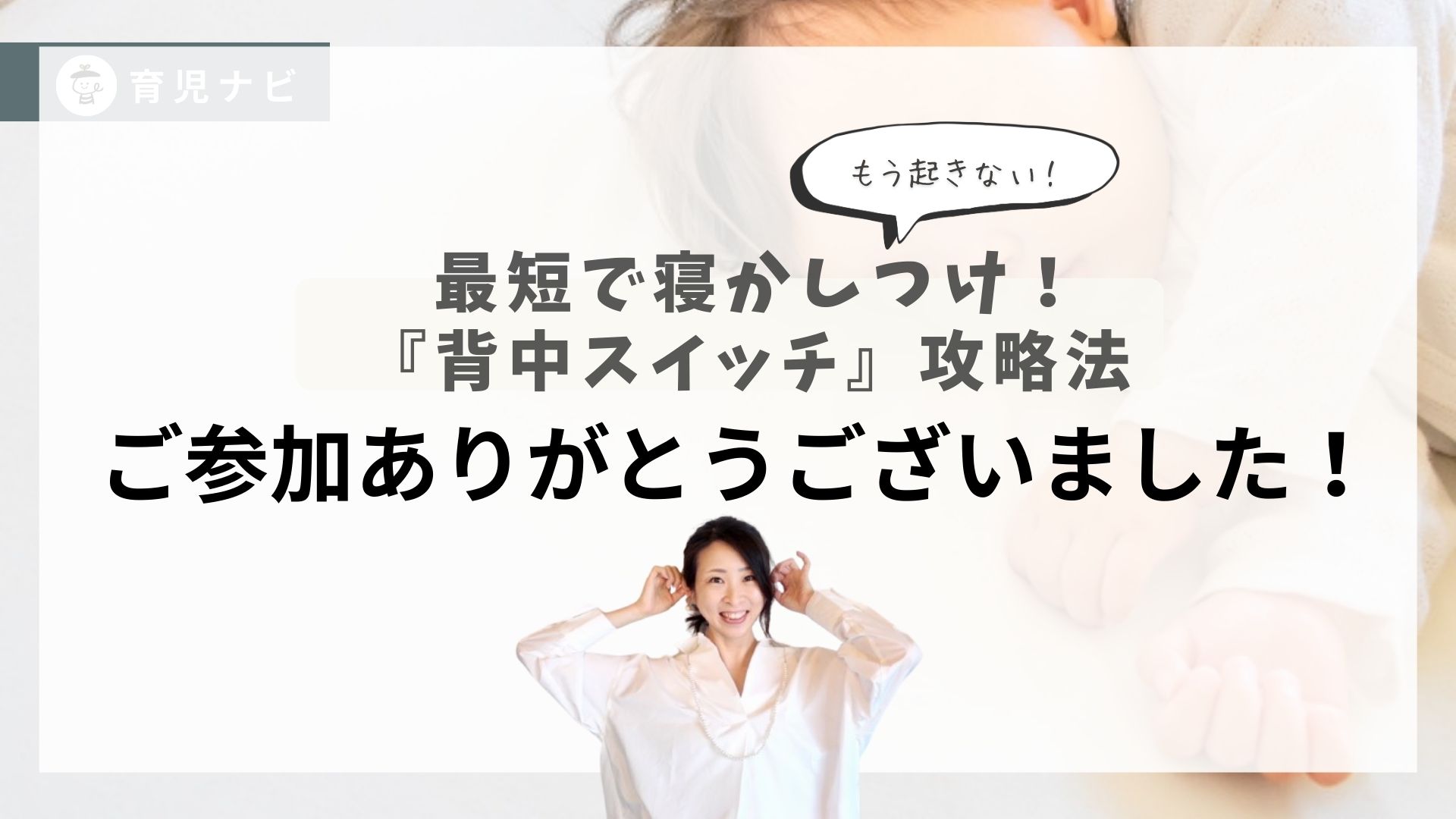

コメント