「もう一回読んで!」
絵本のページ数が終わりに近付くたびに、また言われるんじゃないかと心が休まらない寝かしつけの時間。
なんで何度も読んで欲しがるんだろう。正直読むのがつらい…
この感情は親としてダメなこと?
子どものためには我慢すべき?
そんなことはありません。
誰だって同じ本を何度も読まされるのはかなり忍耐力のいるもの。
自分の気持ちを相手に伝える大切さは例え親子とて平等。
今日の配信は「どうして子どもは何回も同じ本を読んで欲しがるのか」「自分のストレスとの向き合い方」などについて脳科学や発達心理学の視点から、親としての適切な関わり方を一緒に考えていきましょう。
なぜ子どもは同じ絵本ばかり読みたがるのか?
子どもが同じ絵本ばかり読みたがるのは、脳と心の発達に深く関係しています。
① 【記憶と学習のメカニズム】
脳は「繰り返す」ことで情報を定着させるようにできています。
子どもはワーキングメモリ(作業記憶)がまだ発達途中なので、一度読んだだけではストーリーをしっかり覚えられません。繰り返し読むことで、長期記憶に情報を移し、言葉や出来事をより深く理解していくんです。
例えるなら、絵本は何度も通ることでしっかりした「道」が脳にできる、みたいな感じです。
② 【予測と報酬システムの発達】
人間の脳には、物事の「先を予測」し、それが当たると快感を感じる仕組みがあります。これはドーパミンという神経伝達物質が関係していて、成功体験と快感を結びつけてくれます。
子どもは何度も読むうちに、「次はこうなる!」と予測できるようになります。そしてそれが当たると、脳が快感を感じてやる気ホルモン(ドーパミン)が出る。だから、繰り返すこと自体が嬉しくて楽しいんです。
③ 【安心安全のための「ルーティン」】
発達心理学では、子どもは繰り返しを通じて「世界は予測可能で安全だ」と学ぶと言われています。
絵本の展開が毎回同じというのは、子どもにとって「安心できる居場所」みたいなもの。
④ 【自己効力感の獲得】
同じ絵本を読むことで、「このページの次はこれ!」「このセリフは知ってる!」といった体験が増えます。これは、心理学でいう自己効力感(自分はできる!という感覚)を育てることにつながります。
この「自分はわかってる」「コントロールできてる」という体験が、のちの自己肯定感や主体性の土台になります。
繰り返し読むことは子どもの成長にどんな効果があるの?
同じ絵本を何度も読むことは、子どもの成長に多くの良い影響を与えます。
脳の言語領域が刺激され、語彙力や文の構造を自然に覚えるようになります。
また、物語を理解しようとする過程で、集中力や記憶力も養われていきます。
発達心理学では、繰り返し体験は「予測力」と「因果関係の理解」を深めるとされます。
先の展開を予想することで論理的思考や、感情の理解も少しずつ育っていきます。
さらに、登場人物の気持ちを感じることで、共感力や想像力も発達していきます。
繰り返し読みは、ただの習慣ではなく、脳と心の発達を支える大切な学びの時間なんです。
親としてどう対応するのが正解?
毎日のように同じ絵本を読むのは、正直大変なことです。
でも、これは子どもにとって大切な学びの時間だと知っておくことが第一歩。
まずは「またこれ?」ではなく、「これが好きなんだね」「お、脳を成長させるチャンスだな?」と前向きに受け止めましょう。
親が「つらい」と感じる脳科学的な3つの理由
そもそもなぜ親は「つらい」と感じてしまうのか。自分の感情の正体を知っておくと、「あ、自分はこういう理由でイヤと感じているんだな」と俯瞰的に見ることができます。
理由①:自分にとってメリットがないから▶︎【報酬系が刺激されにくい】
人間の脳には「報酬系」と呼ばれる領域があり、新しいことや変化のある刺激に反応してドーパミン(快感ややる気のホルモン)を分泌します。
でも、同じ絵本を繰り返すのは大人にとっては新鮮さがなく、刺激が少ないため、報酬系が働きにくく、「やらされている感」「退屈さ」を強く感じやすくなるのです。
理由②:同じ絵本を読むのが退屈だから▶︎【集中力を使いづらい】
脳の前頭前野は、集中力や感情のコントロールをつかさどる部分ですが、退屈なことや興味の持てないことには注意を向けづらいという性質があります。
同じ内容の絵本を何度も読むうちに「集中力」が枯渇し、脳が疲労を感じてしまいます。
理由③:家事や自分の時間が欲しいから▶︎【育児ストレスによる脳疲労】
子育て中の親の脳は、慢性的な睡眠不足やマルチタスクによって、すでに多くの負荷を受けています。そこに「同じことの繰り返し」が加わると、脳の処理能力が限界を感じやすくなり、ストレスが強くなるのです。
つまり、親が「また同じ絵本か…つらいな」と感じるのは、刺激が少ないことによる脳の飽きと疲れ、そして日常の育児ストレスの影響が重なっているためです。
これは親のわがままではなく、脳の自然な反応なので、自分を責める必要はまったくありませんよ!
正直ツライ…そんな時の上手な対処法
かといえ、できる限りは子どもの気持ちに応えてあげたい。
そんな時はちょっとした変化を加えてみてください。
✅読み方を変える
✅子どもを“参加型”にする
✅時間と回数の“枠”を決める
✅ 家族で“分担”する
✅“絵本を題材にした遊び”へ発展させる
■読み方を変える
▷ 声のトーンやスピードを変えてみる
- キャラクターごとに声色を変える(高い声、低い声、早口など)
- ゆっくり読んだり、あえて早口で読んで「聞き取れた?」と笑いにする
- 例:「オオカミだけ関西弁にしてみよう!」など即興演技も効果的
▷ 歌うように読む
- リズムに合わせてメロディをつける。童謡風にアレンジしても◎
2. 子どもを“参加型”にする
▷ セリフを覚えさせて一部読ませる
- 「このセリフ、○○ちゃん言ってみようか?」と交互読みする
- 特に繰り返しのある本(例:『もこもこもこ』)が効果的
▷ クイズ形式にする
- 「このあと、誰が出てくるんだっけ?」「この動物は何色だった?」
- 正解すると褒めてあげることで、繰り返しもゲーム感覚に変わる
3. 時間と回数の“枠”を決める
▷ 事前に「今日は2冊だけね」と伝える
- 境界を示すことで、親の負担感を軽減
- タイマーや砂時計を使うと視覚的にわかりやすい
▷ 読み時間を短くアレンジする
- 長い本は「今日は前半だけ」「このページだけね」と分割してOK
- 結末を子どもと想像して「続きは明日♪」でも十分満足する子も多い
4. 家族で“分担”する
▷ パートナーや兄姉と交代制にする
- 「今日はママ、明日はパパね」と役割分担して精神的負担を軽減
- 読む人が変わると、子どもにとっても新鮮に感じられる
▷ 祖父母とビデオ通話読み聞かせもおすすめ
- おじいちゃんおばあちゃんが参加できる良い機会にもなります
5. “絵本を題材にした遊び”へ発展させる
▷ 絵本の内容をごっこ遊びに展開する
- 例:『はらぺこあおむし』→紙で食べ物を作って“食べさせごっこ”
- ストーリーを「自分の体験」にすると飽きにくくなる
▷ 絵を描いたり、続きを作ってみる
- 「このあと、ぞうくんはどうしたと思う?」→自由に続きを描いてOK
- 子どもの創造力と表現力も育ちます
6. 「読まない選択」もOKとする
▷ 「今日はちょっと疲れたな…」と正直に伝える
- 子どもも「親が疲れてる」ことを少しずつ理解できるようになります
- 代わりに「なでなでしながら寝ようね」「一緒に絵だけ見よう」など別の形で愛情を伝える
正解は「無理しないで、楽しめる工夫をすること」
繰り返しの読み聞かせは、子どもの成長にとって本当に価値のあることですが、親が無理をしていては本末転倒です。
「ちょっと工夫してみよう」「今日は休もう」──そんな柔らかい選択が、親子にとっていちばんの正解です!
まとめ
毎日のように同じ絵本を読まされて、「またこれか…」と感じるのは、家事育児仕事に追われる親にとってごく自然な反応です。
でも、子どもが満足するまで読んであげればあげるほど、子どもの脳と心を大きく育てることができつかも。そう考えると、「つらさ」から「前向きな時間」へと少しは変わりそうですよね!
\特に重要なポイントは次の4つ!/
・繰り返し読むことで記憶が定着し、言葉を深く理解できる
・先の展開を予測できることで安心感と自信が育つ
・親がつらく感じるのは自然な脳の反応であり、自分を責める必要はない
・無理をせず工夫することが大切で、楽しく続けるための対処法もたくさんある
かといえ親も人間です。疲れていたり、気持ちの余裕がない日もありますよね。
そんなときは、「今日は短く」「今日は動画で」など柔軟に対応していいのです。
繰り返し絵本を読む時間は、単なる“読み聞かせ”ではありません。
それは、親子の心が通い合い、信頼と安心感を育む大切なふれあいの時間です。
大切なのは「毎回完璧に読むこと」ではなく、「一緒に過ごす楽しさ」を感じること。
少し肩の力を抜いて、子どもの「もう一回!」に優しく応えてみてください。
その繰り返しの中に、言葉の力、心の育ち、そして親子の絆がしっかり育っています。
参考文献:『発達心理学への招待』(金子書房)『子どもの脳を育てる本』(講談社)
American Academy of Pediatrics: Early Literacy and Brain Development
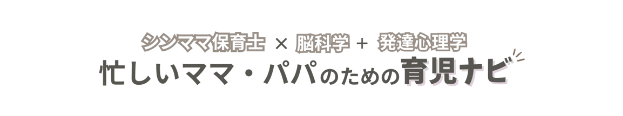



コメント