赤ちゃんや子どもが突然かみついたとき、「どう対策すれば?」「どうやってやめさせるの?」と悩む方は多いはず。とくに初めての育児では、かみつく理由すらわからず不安になってしまいますよね。
本記事では、0〜2歳の赤ちゃん・子どものかみつき行動について、発達や脳の仕組みから丁寧に解説。
感情の背景や接し方、今日からできる具体的な対策ややめさせ方をわかりやすく紹介します。
「なんで噛むの?」が「なるほど!」に変わるはず。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
赤ちゃん・子どもが噛むのはなぜ?
赤ちゃんや子どもが噛むのには、実はちゃんとした理由があります。
全部が全部「困った行動」というわけではなく、成長の一部ということもあります。
子どもがイライラを止められない仕組み
例えば、まだ言葉で気持ちを伝えられない子どもにとって、噛むことは「伝える手段の一つ」
不安や怒り、興奮してしまった時など、未熟な感情をコントロールできないときに噛んでしまいます。
そもそも赤ちゃんや幼い子どもは感情のコントロールが苦手です。
理由は、脳にある「偏桃体」と「前頭前野」が未発達だから。
扁桃体は、「怖い!」「ムカつく!」「イライラする!」などの原始的な感情を処理する場所です。赤ちゃんのころからよく働いており、感情の揺れが大きい時期に活発に活動します。
前頭前野は、感情をコントロールする「ブレーキ」のような役割があります。ただ、この部分は4歳〜思春期にかけてゆっくり発達していくため、1〜2歳児にはまだしっかり機能していません。
なので、「ムカついた!けど我慢しよう」と理性で抑える力がまだ弱いんです。
幼い子程、身体を使って気持ちを放出する
言葉ではなく身体で気持ちを表す段階の子どもは、興奮や不快を体の動きで発散します。怒って手が出る、泣き叫ぶ、そして「噛む」もその一つ。噛むことで自分の中のモヤモヤを外に出そうとしているのです。
実は噛むこと自体に、感覚の調整効果(センサリーモジュレーション)があります。
不安や緊張が高まったときに“噛むと落ち着く”という感覚を、無意識に求めている子もいます。これがいわゆる「感覚的に噛みたい」「口を使いたい」というタイプです。
大人でもありますよね、「緊張するときにガムを噛む」「イライラして歯ぎしりや食いしばりをしてしまう」とかね。アレですね。アレ。
つまり、噛む行動は
・感情をコントロールできない脳の構造
・言葉が未発達なコミュニケーション手段
・感覚調整としての身体的な自己処理
この3つが組み合わさった、発達の一部なのです。
だからこそ、「噛んだら叱る」ではなく、「なにがこの子の心をいっぱいにしたのか」を見つけることが、もっとも効果的な対応になります。
それ以外で考えられる要因は…
もちろん、精神面以外にも理由がある場合があります。
たとえば、歯が生えかけてる時の「むずがゆさ」や、「相手がどんな反応するのか」実験的な好奇心から噛むこともあります。発達年齢によっても噛む理由を探る手掛かりになるので、一緒に見ていきましょう。
年齢・月齢別|噛む理由とその背景
【0〜6ヶ月】口は「世界を知るためのセンサー」
この時期の赤ちゃんは、手に触れたものをなんでも口に運びます。
新生児~1歳頃までを「口唇期」ともいい、口で物の硬さ・温度・形を学んでいます。
噛むというより“吸う・舐める・かじる”動きで、探索行動の一部です。
乳歯の生え始めで歯ぐきがムズムズする「歯ぐずり」も噛む理由になります。
【親の関わり方】
安心できる柔らかいおもちゃや歯固めを与えて見守ってOK。
【6ヶ月〜1歳】「気持ち」と「不快感」を口で表す時期
この頃になると、「快・不快」「好き・嫌い」の感情が少しずつ芽生えます。
でも言葉で伝える力はまだ弱く、不快な気持ち(眠い・お腹がすいた・退屈)から噛むことで表現することがあります。
また、歯が生える痛み(歯ぐずり)や、物への好奇心、抱っこしてほしいなど甘えの欲求にて噛むことがあります。なにかを口に入れる安心しますもんね。ついで歯が痒かったりね、まったく噛まれる方は痛いんだよ。
【親の関わり方】
噛む直前のサイン(モゾモゾ・怒り顔など)に気づき、早めに対応を。
【1歳〜1歳半】「伝えたいけど伝わらない」もどかしさ
この時期は「自我の芽生え」の時期。自分の意志や欲求が強くなってきます。
けれど、語彙はまだ少なく、自分の思いを言葉で伝えることは難しい。
その結果、「おもちゃを取り返したい」「注目してほしい」などの気持ちが噛むという行動で出ることがあります。
脳の前頭前野(感情制御)の発達が未熟なため、衝動的に行動してしまうのも特徴です。
【親の関わり方】
「噛む=伝えたい気持ちの表れ」と理解し、代わりに言える言葉を教えていく。
【1歳半〜2歳】感情爆発の“イヤイヤ期”スタート
いわゆるイヤイヤ期の始まり。自分の思い通りにいかないと、怒り・混乱・ストレスが一気に噴き出します。
でもこの年齢では「怒りを我慢する力」や「気持ちの切り替え」がまだ十分ではありません。
そのため、感情の高まりを噛むことで放出しようとするのです。特に、兄弟や友だちとのトラブル時に見られやすいです。
また、家ではママを噛むのに、パパには噛まない場合、愛着や安心感が強い相手に“ぶつけられる”傾向があるとされます(安全基地理論)。
また、この頃の時期は「相手の反応を“観察する力”が育ち始める時期」です。
子どもは「自分の行動が他人に影響を与える」という因果関係や、「相手は自分とは違う気持ちをもっている」という他者意識(心の理論の芽生え)が出始めます。すると、
「噛んだらママはどうするかな?」
「怒る?笑う?それとも泣く?」
といった“反応を確かめる”行動が増えてきます。
まだまだ子どもは知らない事だらけですからね。悪気はないんです。ないけど、痛いものは、痛い。
【親の関わり方】
・「かんしゃくの一部」と理解し、冷静に対応する。事後のフォロー(共感や言語化)が大切。
・嚙まれたら、しっかりダメなことを伝えるために、二人きりに慣れる場所(部屋や店の隅でもOK)に行き、体に触れながら、落ち着いた声で目を合わせながら伝えましょう。おそらく理解するまで繰り返すことにはなりますが、善悪を伝える上では大変効果的です。
【2歳〜2歳半】“ことば”と“行動”の分岐点
語彙数が一気に増えてくる時期。
それでも感情の処理や状況判断力はまだ未熟で、「言葉で伝える」が間に合わないときに噛むことがあります。
この時期に「噛む=ダメ」ということを学び、徐々に落ち着く子が多くなってきます。
ただし、環境の変化(下の子が生まれた・保育園に行きたくない)などがあると、一時的に噛む行動が復活することもあります。
【親の関わり方】
言葉での表現を促しつつ、噛まなくても伝わる経験を積ませてあげましょう。うまく言葉が出ない場合は、代弁してあげると感情の整理を助長できます。
こんな時は「発達の専門家」へ相談を!
噛む行動が頻繁に続く、暴力的にエスカレートする、言葉の発達が極端に遅れているなどの場合は、専門機関への相談をおすすめします。
発達特性の可能性や、感覚過敏などが背景にあることもあります。
早期にサポートを受けることで、親も子も安心して成長を見守ることができます。
「誰を噛むか」にも理由がある?関係性と噛み行動
赤ちゃんや子どもが「誰を噛むか」には、実は明確な理由があります。
最も多いのはママへの噛みつきで、これは安心感の裏返しとも言えます。
ママは一番近くて甘えられる存在だからこそ、強い感情をぶつけやすいのです。(でも、ママだって痛いんだから、やめて欲しいなら遠慮なくしっかり伝えていきましょうね!)
一方で、兄弟姉妹にはおもちゃの取り合いなどの対等な関係性が背景にあります。伝える手段が他にないから、噛んでしまう。そういうことです。
パパには噛まないという子も多く、それは接する時間の違いや距離感が影響します。もちろん、パパにも噛んできたら、パパを兄弟と同じような対等の存在としてみているか、ママのように甘えられる存在としてみているか。どちらにも成りえます。
つまるところ、相手との関係性や立場により、子どもの噛み方にはバリエーションがあるのです。「誰を噛むか」を手がかりにすると、子どもの内面や欲求がより深く理解できるかもしれませんね。
\もう少し詳しく!/
■ママを噛む:「大好きすぎて爆発しそう」な気持ちのぶつけ先
ママは最も身近で、どんな気持ちも受け止めてくれる“安全基地”のような存在。「感情をぶつけても見捨てない」安心感のある相手です。
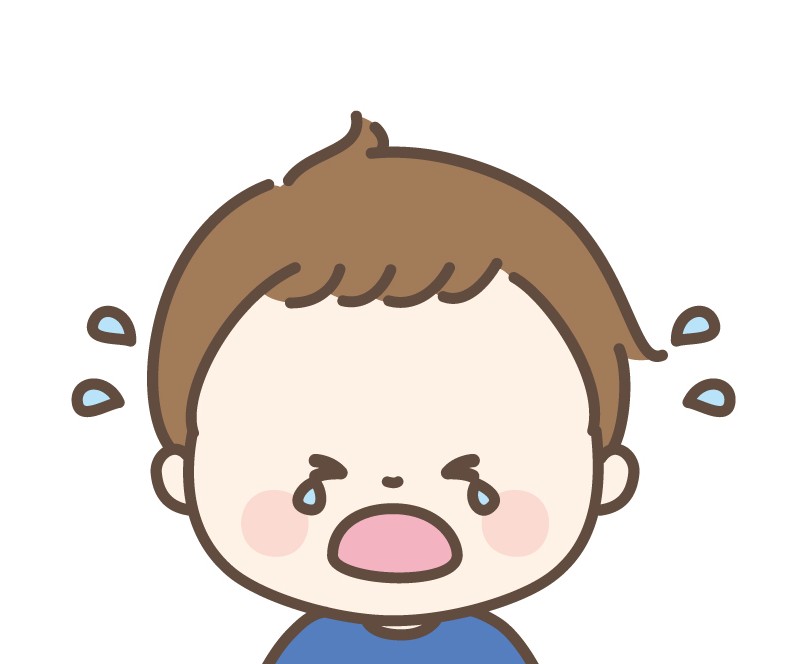
嫌だったの!…でも泣くだけじゃ足りない!ガブッてしちゃう!

ママ、もっとかまって!抱っこして!
親がでできること
①噛んだ直後は一呼吸おいて冷静に「○○って言いたかったのかな?」「悲しかったんだね」と気持ちを代弁する
②スキンシップや言葉での安心感を補う
■兄弟姉妹を噛む:「自分のほうを見てほしい」「取られたくない!」
お姉ちゃんやお兄ちゃんとのおもちゃの取り合い、遊びのなかでのトラブル時に噛むこともよくあります。
これは“嫉妬”や“自己主張”が関係しています。

ママ、わたしのこともちゃんと見て!
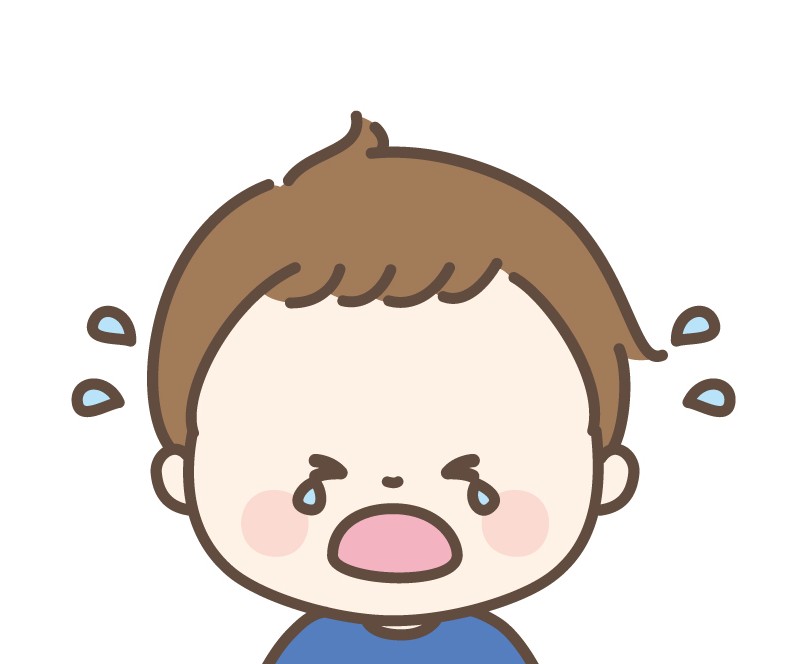
「それ、ぼくが使ってたのに!返してよ!」
親ができること
トラブル前後の状況を丁寧に見て、噛む前のきっかけに注目しましょう。
「それはイヤだったね。でも噛むのはダメだよ」など、気持ちは受け止めつつ、再び噛んだり叩いたりしようとしたら、しっかり止めましょう。
噛まれた兄姉へのフォローも同時に行うのも大切です。
また、もしも愛情不足を感じているようなら、二人の時間を設けて、しっかり愛情を注いであげましょう。愛情タンクの注ぎ方の見直しもポイントです。
噛んだときどう対応すればいい?正しい関わり方
怒鳴らない・叩かない!NG対応とその理由
赤ちゃんや幼児が噛んだとき、思わず「ダメでしょ!」「なんでそんなことするの!」と怒鳴ってしまうこと、ありますよね。
でも、怒鳴ったり叩いたりすると、子どもは“噛んだら怒られた”という恐怖だけが残り、自分の気持ちや相手の気持ちを理解する機会を失ってしまいます。
小さな子どもは、言葉で感情を表現することがまだ難しく、噛むという行動で気持ちを伝えている場合もあります。
叱るよりも、「痛かったね」「○○って言いたかったのかな」と共感や言語化を添えて対応することで、子どもは“気持ちは受け止めてもらえたけど、噛むのはダメなんだ”と学ぶことができます。大人が冷静に対応する姿は、子どもにとって大切な学びの機会です。
噛む前に気づきたい「サイン」や「状況」
子どもが噛むときは、実はその前にいくつかの「予兆」があります。
たとえば、イライラしている・おもちゃを取られそう・眠くて不機嫌・構ってほしいのに言えない…そんなとき、表情が険しくなったり、そわそわしたり、手を強く握りしめたりするなどのサインが現れます。
また、いつも噛むシーンにはパターンがあることも多く、「特定のおもちゃ」「決まった時間帯」など、環境との関連にも目を向けてみましょう。
噛む直前の“火がつく瞬間”を見逃さずに声をかけたり、気をそらしたりすることで、噛む前に未然に防ぐことができます。
予防的に関わることは、子どもにとってもストレスを減らし、親の負担も軽くしてくれます。
噛んだときの声かけ例【年齢別対応】
噛んでしまった子どもにどう声をかけるかは、年齢によって工夫が必要です。
0歳〜1歳前半であれば、言葉よりも表情や声のトーンが伝わりやすいため、「痛いよ」と顔をしかめて、低い声で伝えるだけでもOK。
1歳〜2歳ごろには、「○○って言いたかったのかな?でも噛むのは痛いからやめようね。」と、短い言葉で気持ちを代弁しつつ、しっかりルールを伝えましょう。
2歳以降の子には、「イヤだったら”やめて”って言おうね」など、噛む以外の表現方法を一緒に確認しましょう。また、どうしてイヤだと感じたのか、など深堀すると、語彙力や自己表現の向上にも繋がります。
大切なのは、「あなたがダメ」ではなく「その行動はダメ」と区別して伝えること。子どもの心を否定せず、気持ちは受け止めながらも噛む行為をやめていく方向に導いていくことが、信頼関係と学びにつながります。
噛む代わりに「伝える」手段を育てる(ジェスチャー・言葉)
噛むという行動は、多くの場合「伝えられない気持ちの代弁」です。
だからこそ、噛まずに伝える力を育てることが大切。
たとえば、「かして」「やめて」「つかれた」などの基本的な言葉を、一緒に練習してみるのもいいかもしれません。
まだ言葉が出にくい子には、手を差し出す・首を振る・指を差すといったジェスチャーでも十分です。また、子どもの言語発達に合わせて、絵カードやジェスチャー遊びを取り入れるのもおすすめです。
日常の中で「今の気持ち、こう言えるね」と声をかけるだけでも、伝える手段が少しずつ増えていきます。
噛むことを責めるよりも、「伝える方法」を一緒に探す姿勢が、子どもの心を育てる一歩になります。
噛む子を持つ親が抱えやすい悩みと対処法
子どもが噛んでしまうと、親自身も悩みや不安を抱えやすくなります。
ここでは、よくある3つのケースとその対処法をご紹介します。
「うちの子だけ?」と感じる不安への処方箋
他の子が噛まないように見えると、「うちの子って大丈夫?」と心配になりますよね。
でも、噛む子は実は珍しくなく、発達途中の自然な姿でもあります。
一時的な行動であることがほとんどなので、必要以上に心配しなくても大丈夫です。
噛んでしまった相手の親への対応ポイント
まずは「申し訳ありませんでした」と誠実に謝ることが大切です。
その上で「今後はこう対応します」と伝えると、誠意が伝わりやすくなります。
相手の反応に一喜一憂せず、「今できることをする」姿勢を保ちましょう。
必要があれば保育士や園の先生にも相談し、対応を共有するのも安心につながります。
自分を責めないために:育て方と噛み行動は別の話
「私の育て方が悪いのかな…」と自分を責めてしまうママ・パパも少なくありません。
でも、噛む行動は“親のせい”ではなく、子どもの脳や心の未発達が原因です。
むしろ、噛んだ後の親の対応や寄り添い方こそが、子どもを育てていく力になります。
「うまくいかない日もある」と自分を許すことも、子育ての大切な一部です。
まとめ
いかがでしたか。
本記事では、噛みつきの背景にある感情や脳の仕組み、年齢ごとの対応、親が抱えやすい悩みまで、幅広く解説してきました。
噛みつきをやめさせるためには以下の5つがポイントです。
① 怒鳴らずに、感情を言語化して返す
→ 「痛いよ。でも〇〇って言いたかったのかな?」など、気持ちを代弁。
② 噛む前のサインを観察し、先に気持ちに寄り添う
→ イライラ、不安、眠気、取り合いなど「噛む直前の状況」に介入。
③ 噛む代わりに“伝える手段”を教える
→ ジェスチャー・絵カード・簡単な言葉など、代替手段を育てる。
④ 一貫したルールを示し、落ち着いて伝える
→ 「噛むのはダメ。でもイヤって言えば伝わるよ」と落ち着いて。
⑤ 噛んだ背景を探り、予防的に関わる
→ 注目してほしい・困ってる・試しているなど、噛んだ目的を見抜く。
赤ちゃんや子どもが、人を噛む時の行動は、必ず理由があり、発達の過程で自然に起こることでもあります。その行動の裏には、「どうしていいかわからない」「伝えたいけどうまくいかない」という小さなSOSが隠れているかもしれません。
大人がそのサインに気づき、言葉にして返していくことが、子どもの心を育てる第一歩です。
「また噛んじゃった…」そんなときこそ、子どもが何を伝えたかったのかを想像してみてください。
親のそのまなざしが、子どもの安心感と信頼を育て、やがて噛まずに伝えられる力へと変わっていきます。
子どもはね、親にダメと言われたことをしないように脳で葛藤しているかもしれません。
もしくは、親の言ってる言葉が伝わらずに、なにがダメなのかまだ理解できていないのかもしれません。
いずれにしても、長い目で注意していく必要があります。
しっかり伝えることで、成長発達と共にいずれはなくなっていきますから。
一人で抱え込まず、パートナーや周りの人に相談して、子育てしていきましょう!
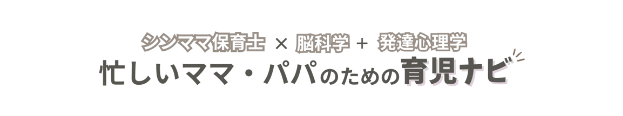
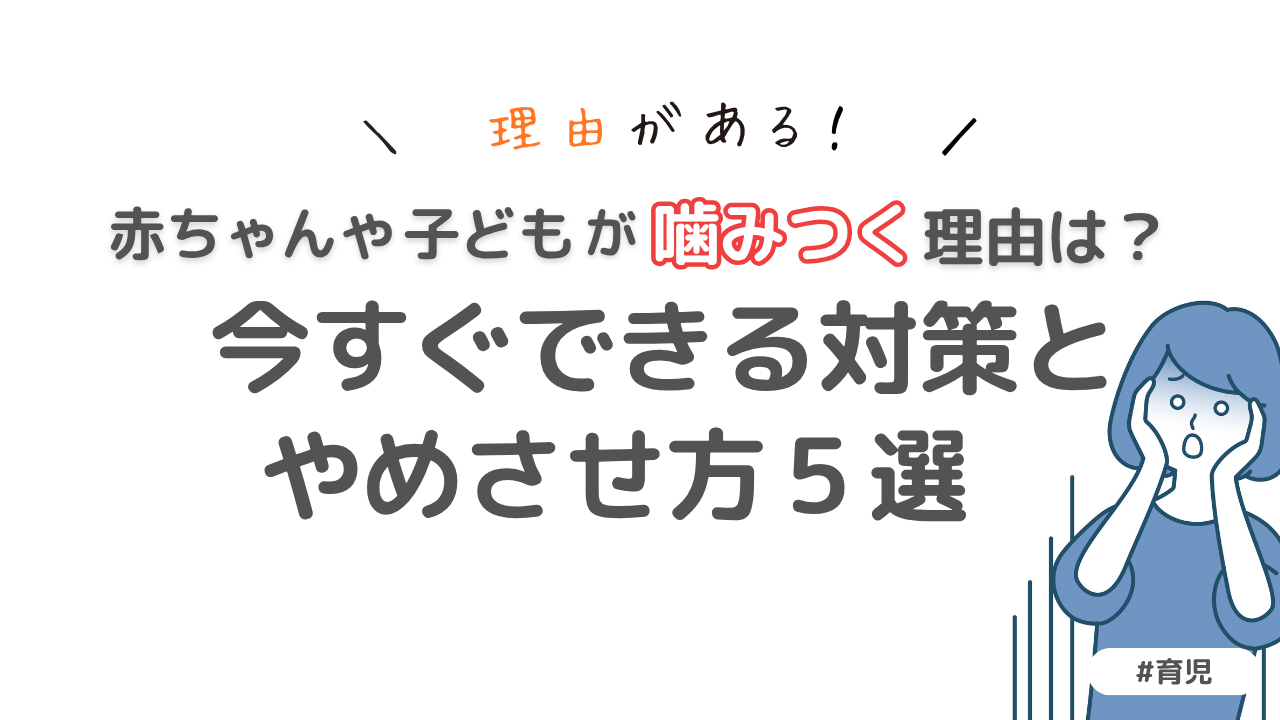


コメント