子ども2人の寝かしつけに悩んでいませんか?
特に年齢が近い兄弟だと、一方が元気いっぱいで遊びたがり、もう一方はぐずり始めて寝かせるタイミングが難しい…という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
当時元保育士である私もそうでした。
「いや、分身しないと無理だよね?」と思っていました。
あいにく分身の術は体得していなかったので、試行錯誤考えた結果、
とりあえず沢山寝て欲しい下の子から寝かしたいと思い、成功率の高い寝かしつけ方を発見!!
今回の配信では保育士やベビーシッターをしてきた中で一番効果的な兄弟児の寝かしつけ方についてコツをお伝えします!
子ども二人を寝かしつけるコツ①上の子に協力してもらう
一番効果的な寝かしつけ方、それはずばり、「上の子」に協力をしてもらうことです。
普段2人同時に寝かしつけようとすると、上の子はおそらく「まだ眠くなーい。」と訴えてきますよね。確かに体力的には上の子はお昼寝をしなくても問題ないかもしれません。
発達心理学によれば3歳児以降はお昼寝をしない子も出てくるとあります。
しかし、上の子はよくても下の子は寝かさなければ。
そこで、上の子に協力を求める、というわけです。
上の子に協力を求める時、理由と目的も含めて伝えると【ピグマリオン効果】も相まって、協力してくれすようになります。
ピグマリオン効果:人は期待されることで、その期待に応えようとする傾向があります。上の子に「あなたが弟(妹)を助ける大事な役割を持っている」と伝えることで、自己効力感が高まり、協力的な行動が促進されます。
では実際にどんな言葉で伝えればいいのでしょうか。
「上の子を味方につける」魔法の言葉
例えば、次のように伝えてみてください。
「○○ちゃん(上の子)は寝なくてもいいと思うんだけど、●●ちゃん(下の子)は寝ないと夜疲れちゃうじゃん。だからさ、●●ちゃん(下の子)が寝るまで一緒に寝たフリして欲しいんだ。●●ちゃん(下の子)は○○ちゃんのことが好きだから真似すると思うんだよね。
それでさ、●●ちゃん(下の子)が寝たら2人で○○しよう!だから一緒に協力してくれるかな?」
黄色いラインの所、特に重要です。
この「特別な時間を約束する」作戦で、上の子はママやパパと遊べることを期待して、下の子の寝かしつけに協力してくれます。
もしも上の子が先に寝てしまった場合は、後からでも約束を守ることが大切です。絵本を長めに読んであげたり、スキンシップを増やしてあげたりすると、次回も進んで協力してくれるでしょう。
子ども二人を寝かしつけるコツ②下の子の特性を理解する
まず下の子を寝かせるために、下の子の特性を理解しておくことが大切です。
下の子って案外単純なんです。
下の子は上の子が大好き。
生意気なことに上の子と体力も発達も知能も同等と思っています。
「上の子がやるなら自分もやる。上の子ができるなら、自分にもできる。」
可愛いですね。
下の子は基本上の子の真似をして過ごしています。
社会的学習理論(バンデューラ):子どもは観察を通じて行動を学びます。特に年の近い兄弟の場合、下の子は上の子をロールモデルとし、「お兄ちゃん(お姉ちゃん)が寝るなら、自分も」という思考に至りやすいです。
ではもしも上の子が寝たらどうします?
おそらく次の2択です。
▶上の子の真似をして寝る
▶遊ぶ対象を親にする
そうしたら遊び相手は大人と変わりますが、
大人も寝たらどうします?
つまらなくなります。
つまらなくなるので、寝てる親を起こして別の部屋に行こうと訴えるか、寝室で1人で遊ぼうと試みます。しかし訴えたとて、みんな寝ていて反応がないのがわかると続きませんし、1人で遊ぼうにも寝室にオモチャがなければ遊べない。
やることがなくなるので、寝てる家族の近くに行き、ミラーリング効果により自然と寝ている家族の真似して就寝という流れです。
下の子は生まれながらに誰かの存在が常にある環境で育ったため、一人で遊ぶには心細さと虚しさがあり、誰かと同じ空間にいたがる特徴があります。なので、同じ寝室という空間で同じ事をするという家族の暖かみに触れると、安心して副交感神経が優位に立ち、入眠しやすくなります。
ちなみにですが、起きてるのが子ども一人になった時、どんな行動に出るのか、ご覧になったことはありますか?
ぜひ薄目を開けて観察してみてください。
急に喃語でお話しを始めたり、覚えたての歌を口ずさんでみたり新たな発見があるかもしれませんよ!
安全で安心な寝室の環境を整える3つのポイント
起きている子どもを薄目で見守る場合、子どもが一人で寝室をウロついても大丈夫なように環境を整えることも重要です。
寝室の環境次第で寝かしつけの成功率にも影響が出ますので、以下のポイントを押さえましょう。
安全な寝室の環境を整える3つのポイント
ママやパパも薄目で起きているとはいえ、状況的にお子様は一人になります。
お子様の安全を確保して最後まで見守れるように、3つのポイントをお伝えします。
①寝室に持ち込むものは「安全で静かなもの」だけ
②寝室にケガにつながる物は置かない
③照明と自然光で様子を見守れる環境を作る
詳しく説明していきます。
①寝室に持ち込んでいいのは「安全で静かなもの」だけ
寝室に持って行ってもいいものは、ぬいぐるみや絵本のみにしておきましょう。
もしも固めのオモチャを持ち込んでいた場合、全員が寝て一人で遊び出した際、オモチャを投げて寝てる人に当たる可能性があり危険です。
なので、寝室には寝かしつけの際に使う本や、飛んできても危険でないぬいぐるみなどを持ち込むようにしましょう。
②寝室にケガにつながる物は置かない
子どもはいつだって予測不可能な行動を取ります。
例えば衣装ケースに登ろうとしたり、物を倒そうとしてみたり。
寝たふりをしている時に危険な行為をされたら、いざという時助けられませんよね。
なのでひとりで登れそうなイスや足場になる衣装ケース、子どもの力で簡単に倒せそうな大きい家具、誤飲に繋がるような化粧品や洗剤などは寝室に置かないようにしましょう。
また、ドアを一人で開けられると出て行ってしまい目が離れてしまうので、ここも工夫が必要かもしれません。
危険物は徹底排除!寝室のレイアウトを見直しましょう。
③照明や自然光で様子を見守れる環境を作る
お子様の様子が伺えるように、ある程度室内が見えてる状態が望ましいです。
たとえばオレンジ色の照明をつけたり、カーテンを少し開けて自然光を部屋に入れながら様子を見られるようにしましょう。
あまりにも眩しいと眠れませんので、ウトウトできるようなほのかな灯り、とくに自然光が望ましいです。外の天気やお子様の好みの明るさで調整すれば◎。
もしも照明を点灯するとしたら、必ずオレンジ色の暖色系にしましょう。
白い光(ブルーライト)は脳を覚醒状態にしてしまいますが、暖色系の光や自然光は脳内のメラトニン(睡眠を促すホルモン)の分泌を助けてくれます。
【実践編】子ども2人を寝かしつける具体的なテクニック
寝る前のルーティンを決める
これ、とても大切です。
寝る前のルーティンを取り入れることで、子どもの脳を入眠モードに切り替えやすくします。
脳の予測機能と習慣化の力:毎日同じ行動を繰り返すことで、子どもの脳が学習し、「これから眠る時間だ」と認識しやすくなります。これにより、脳が無意識にその次の行動を予測し、自然とリラックスモード(副交感神経優位)に入ります。これが寝る前のルーティンの効果を高める理由です。
ルーティンを考える前に覚えて欲しいことが一つ。
それは【食後20分後】くらいに体が眠る準備に入ること。
眠る準備に入ると手足がポカポカしてきます。
これは体内の温度を外に向けて放熱しており、体がリラックス状態に入った証拠です。
なので、腹休めも含めた20分前後に寝る前のルーティンを始めると効率的です。
ルーティンの内容の決め方
ルーティンの内容は静かに行動できるものにしましょう。あまり刺激的な活動をすると脳が醒めてしまいますからね。もしもお子さんが刺激的な活動を求めたら、それはそれで2,3回ほど叶えて、徐々に落ち着いた活動に移行していきましょう。
ルーティンの例と作戦実行までの流れ
- 「ごちそうさま」と言って食事を終える
- 歯磨き・トイレを済ませる
- 絵本やぬいぐるみを選び、寝室へ
- 下の子の絵本を読む
- 上の子の絵本を読む(この間に下の子が寝ることも!)
だんだん読む早さをゆっくりにすると眠気を誘えます! - 全員で「おやすみなさい」
★上の子と作戦決行!
・【親】目をつぶりながら下の子をトントンして寝かしつけ→途中で寝落ちしたフリをする
・【上の子】一緒に寝たふり - 下の子が寝たら、上の子との時間!
▷スキンシップを図ると愛着が深まり、また次も上の子が協力してくれるようになります✨
もう一冊特別に絵本を読んだりして、その後必要であれば寝かしつければOK。
上の子が寝かしつけに協力しやすいよう、ルーティンの途中で作戦を伝えると効果的です。
寝たふり作戦を成功させるコツ
先述した通り、上の子がキーパーソン。上の子次第で成功率は変わります。
まず上の子に、「寝てる時」はどんな状態か聞いてみましょう。
話してるかな?
目や手はどうなってるかな?
と、自分で考えてもらうことで想像力を掻き立てます。
そしていざ実行。
最初は上手くいかなくても、「今の良かったよ!じっと目を閉じていたから寝たのかと思った!」と前向きにフィードバックをしてあげてください。
これを繰り返すことで寝たフリが上手になり、なんならそのまま寝付きもよくなります笑
寝かしつけ中に下の子が泣いしまった時の対応方法
もしも下の子が手足がポカポカしているのに泣いてしまった場合。
まずは5〜15分間胸をトントンしたりスキンシップを図りながら様子を見てみてください。
そのまま触れずに薄目で様子を見るだけでも大丈夫です。愛着形成には問題ありません。
もしも下の子が授乳や抱っこを求めてきたら、それに応えながら、寝っ転がっている上の子に沢山話しかけたり、時折触れてスキンシップを図りましょう。すると、「弟(妹)を抱っこしてるけど、ママ(パパ)は僕のことも見てくれてる!」と、喜ぶはずです。
そして下の子が寝たら、ちゃんと上の子もハグしてあげましょう。上の子だって、ママ(パパ)に抱っこされたいけど、がんばって我慢してたはずですからね。
もし下の子が15分経っても泣いているようでしたら、そんな時は無理に寝かせようとしなくてもいいかもしれません。下の子をベビーカーに入れて、上の子とお散歩、なんて言うのもいいですよね。育児を柔軟にすることで、親も気持ちが楽になることもあります。
まとめ:子ども2人の寝かしつけは工夫次第でスムーズに!
「子ども2人の寝かしつけ」は、多くの親御さんが直面する大きな課題です。上の子と下の子の生活リズムが違うことで、どちらも満足させる寝かしつけ方法に悩むのは当然のこと。しかし、工夫次第でこの悩みを軽減することができます。
この記事では、兄弟児の寝かしつけをスムーズに進めるためのポイントを解説しました。以下に、とくに重要なポイントをまとめます。
寝かしつけ成功のために押さえたいポイント
- 上の子を味方にすることがカギ
上の子に協力をお願いし、「下の子が寝たら一緒に遊ぼう」と約束することで、積極的に寝かしつけに関与してもらう工夫が有効です。 - 下の子の行動パターンを理解する
下の子は上の子を真似する特性があります。上の子が寝ると、下の子も自然と安心して眠りやすくなる傾向があります。 - 安全で安心な寝室環境を整える
寝室には怪我につながる物を置かず、柔らかい照明や自然光を活用して安心できる空間を作りましょう。 - 親子で取り組む寝る前のルーティンをつくる
毎日決まった流れで行動することで、子どもがリラックスし、スムーズに入眠できるようになります。静かな活動を取り入れることがポイントです。 - 泣いてしまった時の柔軟な対応
下の子が泣いた場合は、トントンやスキンシップで安心感を与えましょう。15分以上泣き続ける場合は、無理に寝かせず柔軟に行動を変えることも選択肢です。
上の子と協力しながらのこの作戦は、上の子との信頼関係を深め、下の子も自然に安心して眠りやすい環境が整います。
少しずつ取り入れられる工夫から始めて、ママやパパも無理なく続けられる方法を見つけてください。
兄弟児の寝かしつけがスムーズに進むことで、育児がさらに楽しくなりますように!
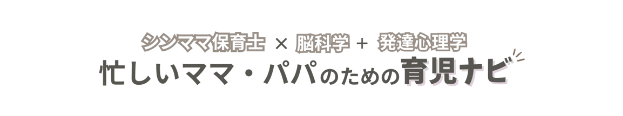



コメント